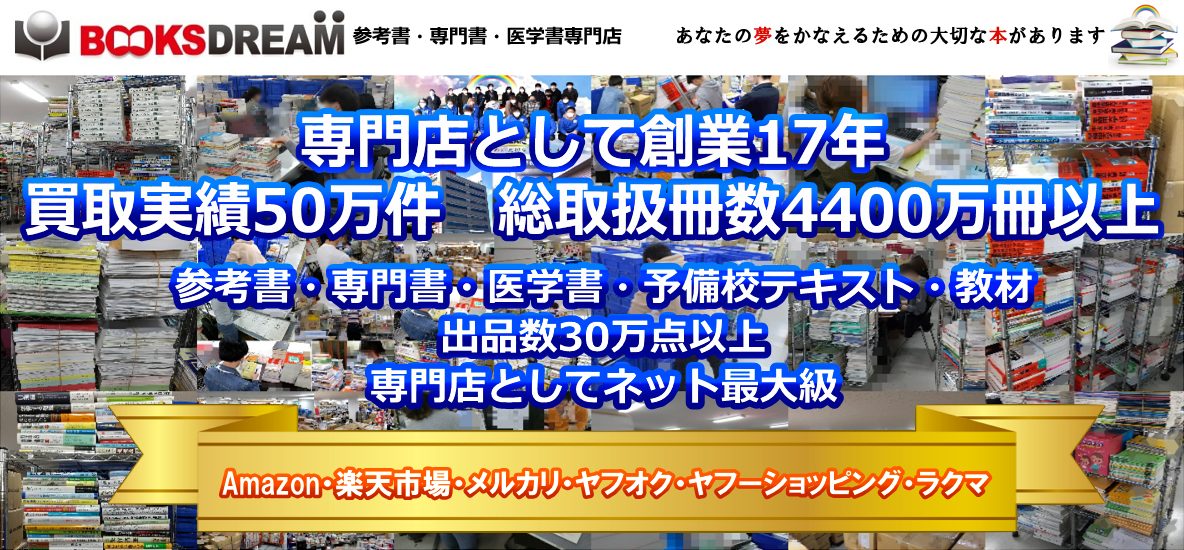赤本は何年分解くべき?限られた年数分の効率的な解き方も解説します

※2024年1月7日更新
ブックスドリーム 編集の”まえだ”です。 いつも弊社ブログをお読みいただきありがとうございます。
大学受験対策の必須アイテムといえば、赤本を思い浮かべる人も多いでしょう。特に受験シーズンとなると、多くの書店でたくさんの赤本が並ぶようになります。
そんな赤本を、何年分解くべきなのかわからない、うまく使いこなせない、と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。今回は、参考書や赤本、予備校テキスト・教材を専門に17年以上買取と販売を行い、800万名以上にご利用いただき、50万件以上の買取と4400万冊以上の取扱い(2026年1月時点)を行ってきた弊社が、「赤本の解くべき年数」と「効率的な使い方」について解説していきます。
目次
赤本とは?
赤本とは、大学入試で過去に出題された問題を1冊にまとめた過去問題集のことです。教学社が発行しており、378大学614点の赤本が販売されています。
全都道府県の大学の過去問を取り扱っており、今では大学受験に必須の存在といえるでしょう。以下では全国の赤本の値段と発売日一覧で紹介していますよ。是非こちらも参考にしてくださいね。
【関連記事】【2025年版】赤本の値段と発売日を一挙解説!地方別、国公立・私立大学を総まとめ
赤本を使うメリット
赤本を使うことによって得られるメリットは、以下のとおりです。
・出題傾向がわかるため、受験に有利になる
・過去問を解くことで、今の自分の実力がわかる
・さまざまな出題形式に対処ができるようになる
赤本では、各大学の数年分の過去問が収録されています。ただ過去問を並べているわけではなく、大学ごとの出題傾向も考えられて問題が選ばれています。出題傾向を絞れることで、どこを重点的に勉強すればいいのかがわかり、効率よく受験対策を練ることが可能です。
そして過去問を解いていくことにより、今の自分の実力を知れるでしょう。入試問題はマークシートや記述、学科によっては論述問題など、さまざまです。赤本によって自分の得意分野と苦手分野がわかるので、得意分野を伸ばすことも、苦手分野の克服にもつながります。
赤本は何年分解くべき?
赤本のメリットがわかったものの、一体何年前まで解けばいいのかわからない、と悩む人も多いはずです。そこで、何年分の過去問を解いていけばいいのかの目安について、解説していきます。
第1志望は直近5~10年分を解く
第1志望の場合は、おおよそ直近5~10年分を解きましょう。多いと感じてしまう人もいるかもしれませんが、過去をさかのぼっても出題パターンが大きく変わらない大学はいくつもあります。そのため、少し昔の過去問でも現在の出題傾向とかぶる点が多いはずです。最低でも5年分は解いておくようにしましょう。
また、なかには出題傾向がコロコロと変わる大学もあります。10年前の問題を解いても、今の出題パターンと合わないことがあるかもしれません。そのような大学の場合は古すぎる過去問をあまりやらずに、直近5年以内の過去問に絞りましょう。
第2志望以降も直近3年分は解いておきたい
第2志望の大学やほかの大学については、直近3年分の問題に対応できるようにしましょう。
まったく対策をとらないとなると、仮に第1志望校に落ちてしまった場合に取り返しがつかなくなります。とはいえ第2志望に力を入れすぎると、本命の第1志望の勉強がおろそかになってしまいます。勉強のバランスにはくれぐれも注意をしましょう。
共通テスト・センター試験は直近5~10年分を解く
2021年度から従来のセンター試験がなくなり、共通テストに変わりました。しかし、まだ年数の経っていない試験のため、出題傾向についてもほとんどわかっていません。
現状では、センター試験の過去問で対策を練るしか方法はないといえます。特に国公立を目指す受験生にとって、共通テストの成績は非常に重要です。最低でも10年分の過去問を解くようにしましょう。
【注意】大学によって入っている年数が異なる
赤本に載っている過去問は、大学ごとに入っている年数に若干の違いがあります。たとえば国公立大学である東京大学や京都大学は7年分と、5年以上前までさかのぼっています。対して私立大学の青山学院大学は3年分、国士舘大学が2年分など、2年~3年前の過去問が中心です。
そのため、収録年数によっては問題が少ない場合もあります。収録されている問題が少ない場合は、それぞれの問題について解説をよく読んだり、応用問題に挑戦したりすることで、問題の対策力を高めましょう。
また、さらに以前の過去問題を解きたい場合は、過去の赤本を手に入れる方法をまとめた以下の記事も参考にしてくださいね。
【関連記事】過去の赤本を入手したい!Amazonなどすばやく調達できる店舗を紹介します
赤本を効果的に解くポイント
手元に赤本があっても勉強の方法を誤ってしまうと、受験対策にはなりません。効果的に赤本を使って、効率よく問題を解く方法を紹介していきます。
時間を計って解く
赤本に取りかかる際に必ず行ってほしいのは、時間を計りながら問題を解くことです。大学入試も共通テストも、問題を解く時間は決められています。時間配分を考えながら問題を解かなければなりません。時間配分を間違ってしまうと、最後まで問題が解けないなどの支障が出てしまうでしょう。
時間も一緒に計りながら赤本を解くことで、本番のときと同様の時間配分で問題を進められます。時間内に問題が解けるようになってきたら、制限時間を短くしてみるのもひとつの手です。制限時間を短くすることによって、本番での見なおし時間を稼げるようになるでしょう。
解答を赤本に書き込まない
赤本を解くときについついやってしまいがちなことが、解答や計算式を赤本に書き込んでしまうことです。赤本自体に解答や計算式を書いてしまうと、その後の復習に活用できなくなってしまいます。
通常のノートに書き込んでもかまいませんが、赤本を活用するのであれば教学社が販売している「赤本ノート」がおすすめです。赤本ノートは入試と同じくマークシート形式になっています。本番と同じように問題を解けるうえに、時間配分や問題の理解度といった分析もできます。
もし赤本に使用するノート選びに困ったら、赤本ノートを活用してみましょう。
完全に理解するまで何周も解く
間違った問題について理解を深めようとしても、1回で完全に理解することが難しい場合もあります。そのときは完全に理解ができるようになるまで、何回でも問題を解くようにしましょう。
中途半端に理解をした状態で放置してしまうと、応用問題などが出た際に対処ができなくなってしまいます。苦手分野の問題となると何回も解くのが億劫になるかもしれませんが、根気強く問題を解いて理解を深めることで、苦手分野の克服にもつながります。
論述形式の問題は先生に添削してもらう
大学受験では、論述形式の問題が出されることがあります。その際の採点は、学校の先生や塾・予備校の先生などに頼むようにしましょう。
論述問題は自分で採点することが難しいものです。自分よりもテストの採点に詳しい教員に添削してもらうことで、より本番に近い採点をしてもらえます。
まとめ
大学受験の必須アイテムである赤本。効率的に赤本を使いこなせるようになれば、合格率は確実に上がります。赤本を何年分解くべきなのか迷うこともあるかもしれませんが、今回ご紹介した目安を参考にしましょう。
・第1志望は直近5~10年分を解く
・第2志望以降も直近3年分を解いておきたい
これから受験勉強をはじめる受験生は、下記の赤本を効率的に解くポイントが大切です。
・時間を計って解く
・解答を赤本に書き込まない
・完全に理解するまで何周も解く
・論述形式の問題は先生に添削してもらう
ぜひ今回の記事を参考にして、志望校合格に向けて赤本を解きましょう!
なお、当ブログでは、「赤本の使い方や買う時期、解き始める時期」「合格に近づく活用アイデア」「赤本のメリットと落とし穴」についても紹介しています。
【関連記事】赤本はいつ買う?いつから解き始める?赤本についての基本を解説
【関連記事】赤本は買うべき?買った赤本の上手な使い方や注意したいポイントも解説します
【関連記事】赤本は買うべき?買った赤本の上手な使い方や注意したいポイントも解説します
【関連記事】赤本の使い方について徹底解説!より合格に近づく赤本活用アイデアもご紹介
【関連記事】赤本には配点が書いてない?どうしても知りたい場合の方法も解説します
【関連記事】【受験】赤本だけで合格は難しい?赤本のメリットと落とし穴を解説
【関連記事】赤本が解けない!その原因とは?点数がとれないときにまず見直したいポイントを解説
【関連記事】赤本・青本・黒本とは?それぞれの違い、どれを使うべきか解説します
【関連記事】【2025年版】赤本の値段と発売日を一挙解説!地方別、国公立・私立大学を総まとめ
【関連記事】共通テストの赤本は買うべきか?黒本・青本との違いや合格に近づく勉強方法を解説
ぜひこれらの記事も参考にして、志望校合格に近づいてくださいね。
また、晴れて大学に合格して、使い終わった赤本を売りたいときは以下の記事も参考になりますよ。
【関連記事】赤本買取でおすすめの6店と買取相場や高く売る方法を徹底解説
こちらも、専門店として赤本の買取と販売を多数行ってきた経験をもとに執筆しています。
ぜひ参考にして、志望校合格後も満足のいく値段で赤本を売却してくださいね。
皆さんの志望校合格をお祈りしています!


![]()
参考書・専門書・医学書、大学の教科書、予備校テキスト・教材を専門に買取・販売しています。専門店として創業16年。45万件以上の買取と4000万冊以上の取扱いを行ってきました。 インターネットから申し込みをして宅配便の着払いで送るだけの簡単買取。全国から送料無料。ご希望の方には段ボール無料送付サービスも行っています。
こちらのブロブでは、当社の最新情報や業務風景、スタッフの紹介の他、参考書・専門書・医学書・予備校テキスト・教材などに関する様々な情報を投稿しています。