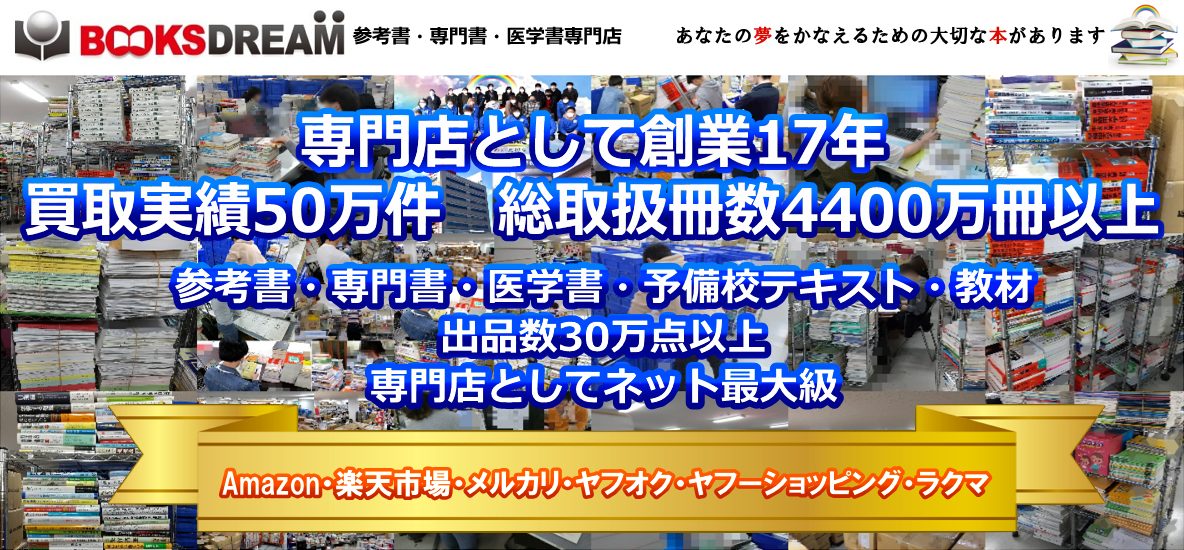参考書の効率的な使い方(読み方)とは?勉強がはかどる活用法を徹底解説!

ブックスドリーム 編集の玉置です。
いつも弊社ブログをお読み頂きありがとうございます。
学校での授業の理解を深める際や、受験勉強に便利な参考書。しかし参考書を買い、そのときのモチベーションは高くても、いざ勉強しようとするとなかなか手につかない…という経験をしたことはあるのではないでしょうか。
そこで今回は、参考書や専門書、医学書、予備校テキスト・教材を専門に17年以上買取と販売を行ってきた弊社が、参考書を買ってから効率よく勉強するためのコツをご紹介します。参考書は、使い方や読み方をしっかりと理解することで、今までより質の高い勉強ができるようになります。
記事の後半では、参考書を使って勉強するときの注意点も解説していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

目次
絶対押さえておきたい!参考書を使って勉強する際の4つのコツ
ここでは、参考書を使って勉強するときのコツを4つご紹介します。勉強としての「心構え」という意味合いもありますので、最初の段階で身につけておきましょう。
これからご紹介するコツを日頃から意識することで、参考書を使う勉強以外の勉強でも、大きな力を発揮しますよ。
参考書の特徴を把握したうえで利用する
まず、購入する参考書の特徴を把握したうえで利用することが大切です。
それぞれの参考書には、必ず「本書の使い方」や「はじめに」というページがあります。そのページでは、参考書の特徴や、効率的に活用するための方法が書かれているので、参考書ごとに特徴を把握しましょう。そうすることで、より効率的な勉強につなげられます。
たとえば、テキストベースよりもイラストや図解などを多く使われているほうが勉強しやすいのであれば、図解やマンガでわかる系の参考書を選ぶと、効率的に勉強できます。




参考書を選ぶ際も、書店であれば立ち読みが可能です。最初に書かれている参考書の使い方を確認し、自分にとって使いやすそうなものを購入しましょう。
複数の参考書を読むより、一つの参考書をマスターする
参考書を使った勉強でやりがちなのが、さまざまな種類の参考書を読んでしまうことです。一見、問題ないように感じるかもしれませんが、実はもっとも非効率になってしまいます。
先ほども述べたように、参考書ごとに使い方や表現の仕方が変わります。複数の参考書を読んでしまうと、無意識に混乱した状態で頭にインプットされてしまうでしょう。その結果、「あの参考書では〇〇って書いてあるけど、この参考書は△△と書いてあったな…」と、試験本番で混乱してしまい、間違えてしまいます。
このようなことを避けるためにも、まずは購入した参考書一冊を、完全にマスターするようにしましょう。参考書は一冊だけでもとても作り込まれています。じっくりと読み込むことで、試験や受験に通用する学力を身につけることは十分可能です。勉強は量にこだわるよりも、まずは質にこだわってみると、成長スピードも速くなりますよ。
参考書に直接書き込んで自分の苦手なポイントをわかりやすくする
参考書を教科書のように使っていては、なかなか勉強の質も上がりません。参考書で気になった箇所や苦手なポイントに直接メモなどを書き込んだり、ふせんを貼っておいたりしておくと、あとで見返したときにわかりやすくなります。

特にトピックが多い参考書だと、読み込むのに何日もかかってしまうでしょう。その都度書き込んでおかないと、また同じ箇所でつまずいてしまう可能性があります。
ただし、演習問題や問題集になっているものは、直接書いてしまうと繰り返し演習ができません。あくまでも「理解する」という部分で、苦手だと思った箇所に書き込みましょう。
参考書への書き込みのコツは以下の記事でも紹介しています。売る際に支障のない書き込みの方法も紹介していますので、是非合わせてお読みください。
定期的に自分でテストを行い、アウトプットの機会を作る
参考書を使って効率よく勉強をするには、必ずアウトプットができる場を設けるようにしましょう。たとえば英語の場合、参考書を読んで文法や英単語を覚えるという作業は「インプット」です。いわゆる脳に覚え込ませている状態になります。人間は、覚えた公式や単語を使う問題などを解いて、「アウトプット」しないとなかなか脳に定着しません。
たとえば、学校で受けている授業を1回聞いて、定期テストで100点が取れるでしょうか。一般的には難しいですよね。このように、一度インプットしただけでは脳に定着しません。必ずインプットとアウトプットをセットにして勉強しましょう。

ちなみに、人間はインプットをするよりも、アウトプットしているときのほうが記憶に定着しやすいといわれています。これから参考書を使って勉強するときは、インプットとアウトプットを意識して勉強するようにしてみましょう。
例題がわからない場合はすぐに解説を読む
学習参考書が問題集の場合、参考書に登場する問題は、多くのケースで「例題」と「練習問題」の2種類に分かれています。例題でつまずいてしまった場合は、すぐに解説を読んで理解を深めましょう。
例題はあくまでも問題の解き方を知るために用意されたコンテンツです。一方の練習問題は、例題を解くなかで得た知識が身についているかどうかを確かめるためのコンテンツとして用意されています。
つまり、例題は「わからなくて当たり前」と考えても問題ありません。例題がわからずに困った場合は、ページの直下や次のページなどに用意されている回答・解説を読み、完全に理解できるようになるまで繰り返し参考書を読みなおしましょう。
参考書を使って勉強するうえで注意したい3つのポイント
参考書を使って勉強するときのコツがわかったところで、注意すべきポイントもあわせてご紹介します。
もちろん参考書は、勉強を「サポートする」ためにはとても便利なものです。しかし、「あの参考書をやったから大丈夫」など、参考書を利用することが手段から目的に変わってしまうのは危険です。今から参考書を買って勉強を進めていくのであれば、下記でご紹介するポイントを必ず守るようにしましょう。

参考書を買っただけで勉強した気にならない
まず一つめに気をつけるべき点が、参考書を買っただけで満足してしまうことです。
参考書を書店で購入するときは「帰ったらすぐにでもこの参考書を使おう」と思っていても、いざ帰宅すると勉強しないというケースも多々あるでしょう。このようにただ参考書を買っただけでは、まったくの無意味になってしまいます。
そのため、「なぜ参考書を買うのか?」「なぜこの参考書を選んだのか?」と必ず考えるようにしましょう。あくまでも参考書は、勉強をサポートするためのものです。買っただけではなんの効果もないことを覚えておきましょう。
参考書で勉強した結果をすぐに求めない
よくある勘違いは、「参考書は一周すればOK」という考えです。しかし先ほども述べたように、覚えたものを知識として定着させるには、インプットとアウトプットを繰り返し行う必要があります。参考書を一周だけ読み終わっても、ほとんどが定着していないのが事実です。
参考書は目安として、3〜4周はするようにしましょう。ただし、あくまでも周回数は目安です。参考書を周回するのは回数が目的ではなく、完全に定着させることが目的です。そのため、ご自身の判断である程度理解度が高まってきたら、次の参考書にうつりましょう。
期限を決めずに着手しない
参考書を使う際は、必ず期限を設けるようにしましょう。明確な期限がないと、必ずだらけてしまいます。
たとえば英単語1900語であれば、1日50単語を覚えるという期限を決めます。そうすると、38日間でひと通り終わるでしょう。
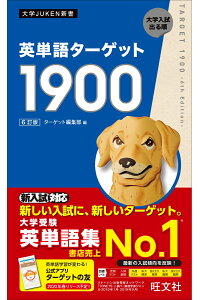
このように明確な期限を設けることで、達成感も得られ、勉強への意欲も出てきます。
参考書に上手な書き込みをするために押さえたい4つのポイント
参考書は、ワンポイントなどを書き込むといった使い方をする人が多い本です。しかし書き込み方のコツを知らないまま書き込みを入れると、見にくくて使いにくい参考書になってしまいます。
上手な書き込み方のポイントは以下の4つです。
書き込みに適している参考書を選ぶ
前提として、参考書には書き込みに適しているものと適していないものがあります。書き込みを入れる使い方をする場合は、参考書を購入する前に中身を確認して、書き込みに適している参考書を選んでください。
たとえば英単語などを暗記する項目が多い英語の参考書や、文法の解説部分が多い英語の参考書は書き込みに適しています。各ページに空白が多ければ、書き込みをするスペースも多く、より書き込みやすい参考書といえるでしょう。
反対に、問題集など演習問題が多い参考書は、書き込みに適していません。問題部分に回答などを書き込んでしまうと、問題を繰り返し解けなくなってしまいます。問題集に書き込みを入れたい場合は、ページをコピーするなどして別紙を作りましょう。
要点が簡潔にまとまるように書き込みをする
あまりにも多くの書き込みを入れると、要点がぼやけてしまい、苦手な箇所や覚えるべき場所が見つかりにくくなります。参考書に書き込みを入れる際は、要点を簡潔にまとめるように意識しましょう。
参考書の余白が黒く埋まると、何となく勉強をしたような気分になりがちですが、書き込むことが参考書を使う目的になってはいけません。書き込みはあくまでも参考書の解説を補完するために入れるものなので、情報量は最小限に抑えましょう。
書き込みは原則として解説部分に行う
書き込みをする箇所は、原則として参考書の解説部分のみです。演習問題などに回答を書き込んでしまうと、参考書を読みなおしたときに答えがわかってしまい、繰り返し勉強することができません。
参考書には、書き込みをしてよい箇所と、書き込みをしてはいけない箇所があります。参考書を繰り返し読み返す姿をイメージしながら、どの箇所に書き込みがあると邪魔になるのか・ならないのかを考えて書き込みをしましょう。
有益な情報だけを書き込む
参考書は将来的に不要になるケースがほとんどなので、買取店を利用することも想定しながら使いましょう。
書き込みを入れるのは参考書の使い方としてごく一般的なため、多少の書き込みがあったとしても買取に応じてもらえる場合がほとんどです。しかし、それは「講師のアドバイス」や「解説の要点」などの有益な情報に限ります。
自分にしかわからないような言葉や表現の書き込みや、落書きとみなされるような書き込みは減点の対象になるため要注意です。大学受験後などに参考書を売却する予定がある場合は、参考書をメモ帳代わりに使わないように意識しましょう。
自分に合った参考書の選び方
参考書は多くの出版社が発行しています。英語の参考書一つを取っても、その数は数千冊・数万冊単位に及ぶため、どの参考書が自分に合っているのかわからずに困っている方も多いのではないでしょうか。
自分に合った参考書の選び方としては、以下の4つを挙げられます。
現状のレベルに合った参考書を選ぶ
もっとも重要なのは、現状の学力レベルに合った参考書を選ぶことです。
ついハイレベルな参考書を選んでしまいがちですが、内容が難しすぎると勉強の効率が下がり、自信も失ってしまいます。反対にレベルが低い参考書を選ぶと、その参考書から学べるものが少なく、自信過剰な状態に陥るかもしれません。
手に取った参考書が現状のレベルに合っているかどうかは、練習問題の正解率から割り出せます。5割~6割の問題に正答できる参考書は、入試の合格点の特典率とも一致するため、現状のレベルに合っていると判断しましょう。
7割以上の問題に正答できる場合や、反対に2割~3割程度しか正答できない場合は、現状のレベルに合った参考書とはいえません。
書店で内容を確認する
参考書はインターネットでも購入できますが、可能な限り実際に書店で内容を確認してから選ぶことをおすすめします。こうすることで、先述したような「現状のレベルに合った参考書」も見つかりやすくなるでしょう。
評判がよい参考書だとしても、自分のレベルや使い方に合った参考書でなければ、使いこなすことはできません。両親や兄弟姉妹、先輩から参考書を譲り受けることも避けて、自分自身で選んだ参考書を使うことがポイントです。
学校や塾の先生からおすすめされた参考書を選ぶ
どうしても自分自身で参考書を選べない場合は、学校や塾の先生にアドバイスを求めてください。身近な教師や講師は、あなたの現状のレベルを深く理解しています。参考書にも詳しい場合が多く、最適な参考書を選んでもらいやすいです。
明確な志望校がある場合は、その志望校に合格した先輩が使っていたものと同じ参考書を購入するのもおすすめできます。また、インターネット上などで志望校に合格した人物を探し、合格体験記を見ながら参考書を選ぶのもOKです。
実際にその参考書を使っている場面をイメージする
参考書の内容や評判がよいと思って購入しても、実際に使い始めてみて「自分には合っていない」と感じると本棚の肥やしになってしまいます。参考書を購入する前に、実際にその参考書を使っている場面をイメージして、問題なく活用できるか考えてみましょう。
多くの参考書には、参考書の使い方について明記したページがあります。また、「イラストが多い参考書」「解説が丁寧な参考書」など、参考書の特徴は本によってさまざまです。自分が読みやすい、使いやすいと直感できる参考書を選ぶのもポイントになります。
まとめ
今回は参考書を使って勉強するコツと、その注意点をご紹介しました。特に意識して頂きたいのは、参考書はあくまでも勉強をサポートする手段であって、目的ではないことです。そのうえで、参考書の特徴を把握し、まず一つの参考書をマスターしましょう。参考書に直接書き込むと、苦手なポイントもわかりやすくなります。
参考書の正しい使い方をマスターして、効果的な勉強を実現していきましょう。
この他にも当ブログでは、「赤本の使い方や買う時期、解き始める時期」「合格に近づく活用アイデア」「効率的な解き方」「配点の調べ方」「販売時期」など赤本に関する役立つ情報を紹介しています。
参考書だけでなく赤本も上手に活用できれば、志望校合格にぐっと近づくことができます。ぜひこちらも参考にして勉強に取り組んでください。
参考書や赤本の効率的な使い方と使う意味(目的)を知り、合格へ近づいていきましょう。
最後までお読み頂きありがとうございました!


![]()
参考書・専門書・医学書、大学の教科書、予備校テキスト・教材を専門に買取・販売しています。専門店として創業16年。45万件以上の買取と4000万冊以上の取扱いを行ってきました。 インターネットから申し込みをして宅配便の着払いで送るだけの簡単買取。全国から送料無料。ご希望の方には段ボール無料送付サービスも行っています。
こちらのブロブでは、当社の最新情報や業務風景、スタッフの紹介の他、参考書・専門書・医学書・予備校テキスト・教材などに関する様々な情報を投稿しています。