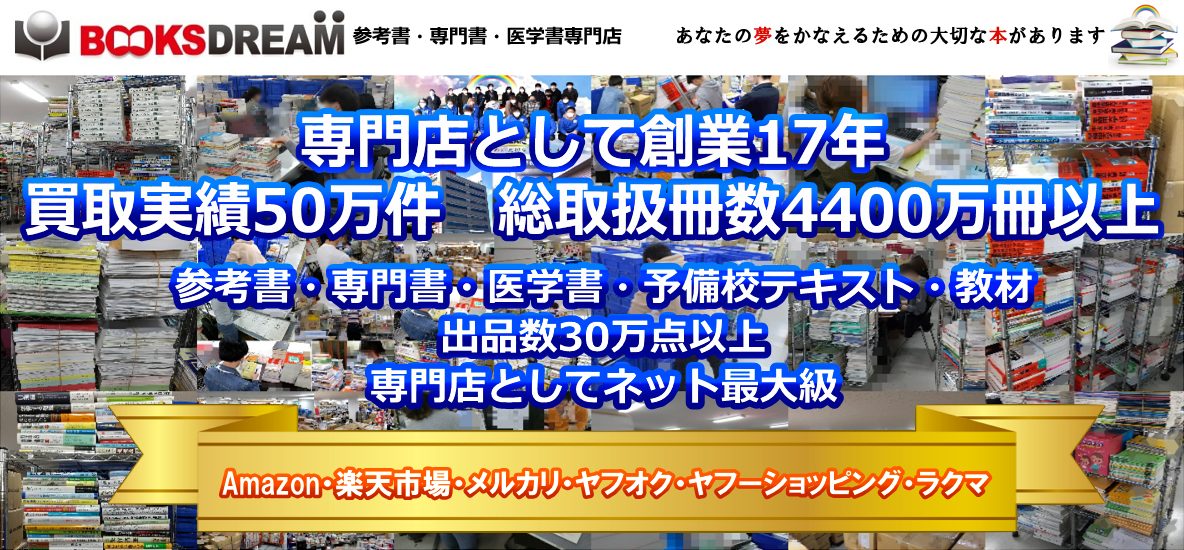ノートを使った勉強法は時間の無駄?おすすめ勉強法からノートまとめのコツまで解説

ブックスドリーム 編集の玉置です。
いつも弊社ブログをお読み頂きありがとうございます。
授業中や勉強において必需品であるノート。なかには、授業内容をノートへ丁寧にまとめている人もいるでしょう。しかし、ノートをまとめているだけでは、成績が上がりません。
そこで今回は、「ノートの使い方がわからない」「ノートを使った勉強方法が知りたい」という人のために、参考書や専門書、医学書、予備校テキスト・教材を専門に17年以上買取と販売を行ってきた弊社が、ノートを使ったおすすめの勉強法とまとめ方のコツについてお伝えしていきます。

目次
ノートにまとめる勉強法は時間の無駄?
板書をノートへきれいにまとめるだけであれば、時間の無駄です。ただし、ノートを作る目的が明確なら問題ありません。
ノートを作る目的は、以下のようなものがあります。
・理解を深める
・見返して苦手分野を克服する
・覚えていない知識の整理
・演習用
以上のような目的もなく、「きれいにまとめる」「ノート作りに満足して勉強した気になる」というのは、勉強をしているのではなく、作業をしているだけの時間です。
ノートを使ったおすすめ勉強法
それでは、ノートを使ってどのように勉強をすればいいのでしょうか。おすすめの勉強方法を4つご紹介します。
1.左ページに予習・右ページに授業の板書をする
2.苦手な部分を集めたノートを作る
3.付箋をメインにしたノートを作る
4.参考書の答えを書き込む
ひとつずつみていきましょう。
①左ページに予習・右ページに授業の板書をする
まずは、見開き1ページに予習と板書を書く方法です。左ページに予習、右ページに板書をすることで、自分が予習で間違えた点や疑問に思った点がすぐにわかります。
また、授業の復習も次のページで行えば、1回の授業内容が3?4ページでまとまります。予習・復習ノートを別に作る必要がなく、効率的です。
②苦手な部分を集めたノートを作る
2つ目の方法は、苦手な部分を1冊に集めたノート作りです。科目ごとにノートを作らず、1冊に全科目の苦手部分をまとめると、試験前にはノート1冊だけで事足ります。苦手な文法や暗記すべき箇所、間違えやすい問題を書き込み、何度も見返して苦手な部分をなくしていきましょう。
③付箋をメインにしたノートを作る
3つ目は、付箋を使ったノート作りの方法です。授業中のメモやわからなかった点、重要な点や苦手な部分を付箋に書き込んでいきます。

この方法は、付箋を入れ替えながら整理したり、授業で使ったプリントをあとから貼れたりと、修正ができる点が大きなメリットです。
④参考書の答えを書き込む
最後は、参考書の答えをノートに書く方法です。参考書や問題集の答えを直接書き込むのではなく、ノートに書いていきます。
参考書に直接答えを書き込むと、2回目に解く際に答えがわかってしまいます。そのため、実際は解けなかった問題もわかった気になり、学習の効果が薄れてしまうでしょう。
ノートに答えを書き込めば何度でも復習ができます。スペースも広いため、間違えた問題に対するメモなども書き込めます。
気をつけよう!ノート作りがおすすめできない人の特徴
ノート作りのおすすめ方法をお伝えしましたが、すべての人がノート作りに向いているわけではありません。ノート作りがおすすめできない人の特徴は、以下のとおりです。
・時間がない人
・完璧主義の人
理由をみていきましょう。
時間がない人
受験までの時間が少ない人は、ノート作りをおすすめできません。本番までの時間が迫っているなかでノート作りをはじめてしまうと、ノートを作るだけで受験を迎えてしまいます。残り時間が少ない人は、ノート作りに専念せずに違う方法で勉強を進めていきましょう。
完璧主義の人
「完璧主義」「きれいなノートにしたい」人も、ノート作りは向いていません。より丁寧に字を書こう、見た目もわかりやすくしたいなど、細かい部分に目がいってしまうため、「ノートを完璧にまとめること」が目的に変わってしまいます。
あくまで、ノート作りは自分が理解をするためのものです。細かい点が気になる人や完璧にしてしまう人は、ノート作りをおすすめできません。
ノートのまとめ方のコツ5つ
ノートをまとめるには、ルールを決めておくと便利です。5つのコツをご紹介します。
1.見出しをそろえる
2.余白をとる
3.使う色は絞る
4.コピーを有効活用する
5.時間を使いすぎない
それぞれ説明していきましょう。
①見出しをそろえる
まずは、見出しをそろえることです。大見出し・中見出し・小見出しを、それぞれどのように書くか決めます。一度、例をみてみましょう。
■大見出し・・・赤色のマーカー
■中見出し・・・青色のマーカー
■小見出し・・・緑色のマーカー
上記のように、見出し別に色を変えるだけでもわかりやすくなります。また、記号の追加や文字の大きさを変えることもおすすめです。自分が見やすく、わかりやすいように見出しを設定しましょう。
②余白をとる
2つ目のコツは、全体的に余白を作ることです。余白を大きめにとったほうが、メモやポイントを追加しやすくなります。
余白のない状態では追加情報を書き込むスペースがないため、上から重ねるように書くことになり、振り返ったときに「何を書いたのだろう」となることも。そのため、あとからでも書き込めるほどの余白はとっておきましょう。
③使う色は絞る
3つ目は、使う色を絞ることです。カラフルなノートはきれいかもしれませんが、学習においては重要なポイントがわからなくなってしまいます。使う色は黒色+2~3色程度がおすすめです。
さらに、色別に意味を決めておくとよいでしょう。たとえば、赤・青・緑のボールペンを使う場合に、以下のような意味を決めます。
■赤・・・重要箇所
■青・・・暗記すべきもの
■緑・・・先生の言ったこと、疑問に感じた部分のメモ
「メモは何色を使おうかな」と悩む必要がないため、時間の短縮にもつながります。

また、授業中の板書をする際は、あとからマーカーで色をつけるのもひとつの方法です。授業中はすべて黒を使い、あとから重要箇所やポイントを色分けすれば、先生の話に集中でき、復習にもつながります。
④コピーを有効活用する
4つ目は、教科書や参考書をコピーする方法です。簡単な図や表であれば自分でも書けますが、複雑なものや効率を考える場合は、必要部分をコピーしてノートに貼り付けましょう。手間がかからず時間も短縮できます。
⑤時間を使いすぎない
最後のコツは、ノート作りに時間をかけすぎないことです。ノートをまとめているうちに、「レイアウトをこうしよう」など、ノート作りの作業に没頭する可能性があります。
繰り返しになりますが、ノート作りはあくまで勉強することが目的です。ノートをまとめることを目的にしないようにしましょう。
まとめ
ノートを使った勉強方法は、目的さえ見失わなければ自分だけの参考書になります。しかし、まとめることに満足している場合は、勉強をした気になっているだけです。入試までの貴重な時間を無駄にしているため、あくまで理解を深める、暗記する、苦手を克服するといった「勉強」が目的になるノート作りをしましょう。
自分のメモや情報が詰まったノートは、受験当日も心強い存在です。ここでご紹介した勉強法やまとめ方のコツを参考にして、ほかにはない自分だけのノートを作ってみましょう。
なお、当ブログでは、参考書や問題集・赤本の効果的・効率的な使い方や参考書の選び方、おすすめの参考書についても紹介しています。
受験生におすすめしたい手帳とその使い方や成績を上げるためのルーズリーフの効果的な使い方については以下で紹介しています。
ぜひこれらの記事も参考にして、志望校合格に近づいてくださいね。
また、晴れて志望校に合格した後に参考書や問題集・赤本を効率的に処分するコツや高く売るためのコツ、おすすめの買取店も紹介しています。
受験勉強は心が折れそうになることもあるかもしれませんが、是非これらも参考にして、充実した受験ライフを送ってくださいね。
皆さんの志望校合格をお祈りしています!


![]()
参考書・専門書・医学書、大学の教科書、予備校テキスト・教材を専門に買取・販売しています。専門店として創業16年。45万件以上の買取と4000万冊以上の取扱いを行ってきました。 インターネットから申し込みをして宅配便の着払いで送るだけの簡単買取。全国から送料無料。ご希望の方には段ボール無料送付サービスも行っています。
こちらのブロブでは、当社の最新情報や業務風景、スタッフの紹介の他、参考書・専門書・医学書・予備校テキスト・教材などに関する様々な情報を投稿しています。